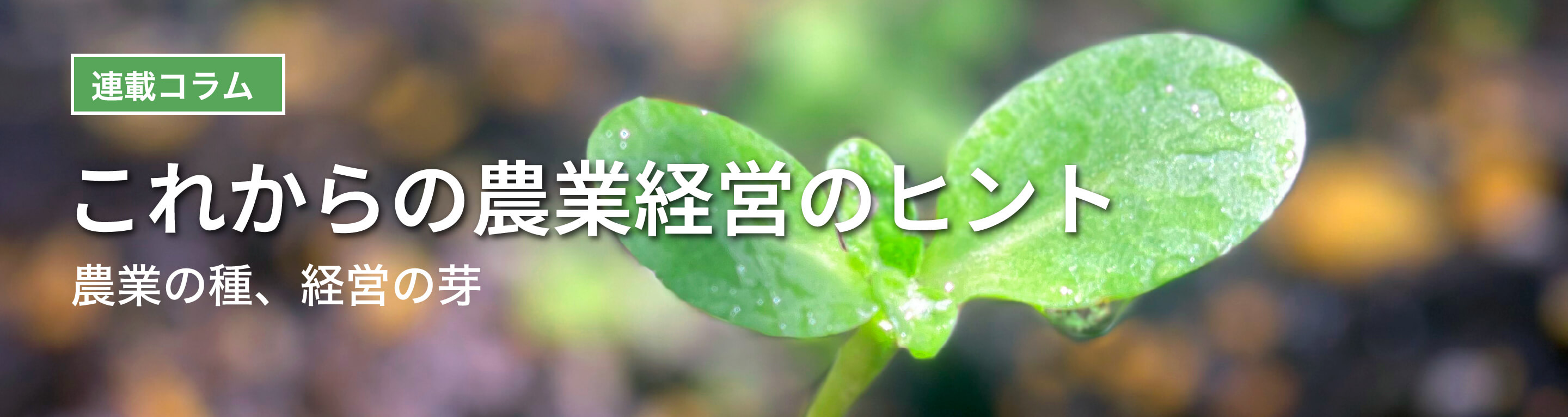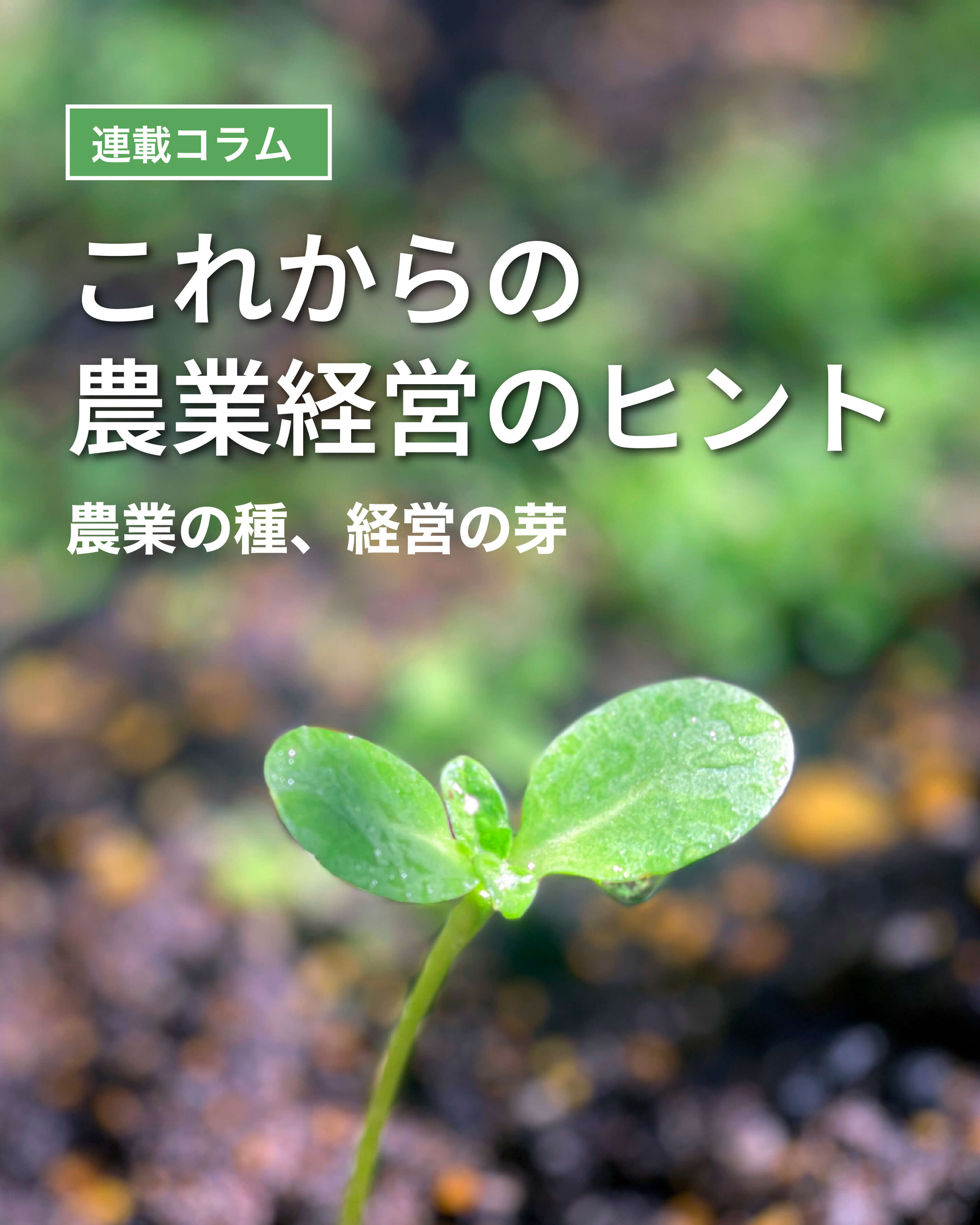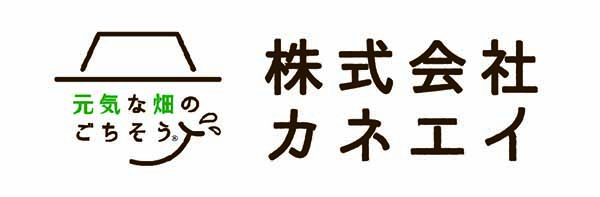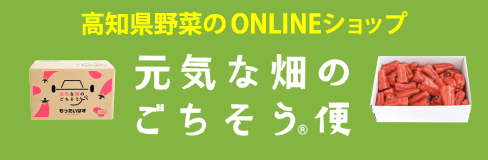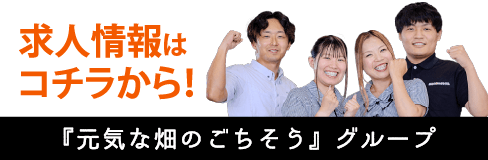今回は、経営が悪化する特徴について解説します。東日本大震災、毎年のように発生する異常気象、それによる米価下落、コロナ禍など、この10年間は農業経営者にとって大変な外部環境の連続でした。そんな中で、筆者は様々な農業経営者を見てきましたが、同じ外部環境下でも経営が悪化する特徴には傾向があることに気がつきました。筆者は東北の農家さんを間近に見てきました。地域が違っても当てはまることが多いのではないかと思います。 そういう意味でも、「やってはいけないこと」、「注意したほうがいい」という観点で読んでいただきたいです。
経営が悪化する特徴は、以下の5点です。
- ①急激な規模拡大や新規品目への変更
- ②身の丈以上の投資
- ③無理な雇用や問題のある雇用
- ④原価とかけ離れた契約販売
- ⑤事業主が一人で背負い決断
①急激な規模拡大や新規品目への変更
農家さんは、利益が上がっていないのは規模が足りないからだ、と思う方が多いです。 そして、急激に規模拡大(例えば、大規模なハウスへの投資)を実行する。その結果、土壌条件が以前と大きく変わり、栽培管理の対応不足が発生して収量を大きく落とす。
今までの面積なら経験豊富なパートさんや家族で管理できていましたが、急激な面積拡大により全員が忙しくなってしまい、作業に追われて結果収量を大きく落とす。新たな人員増加をしたものの、新しいパートさんの育成が十分できずに追いつかない。
工場の世界では、規模を大きくすれば効率が良くなります。しかし、農業では規模を大きくすると効率が悪化してしまいがちです。 ベテラン農家ほど、急激に拡大すれば経営は良くなると考える方が非常に多いので問題です。
同じく、コロナ禍などの外部環境の変化に動揺してしまい、急に今まで収量が上がっていた品目をやめて、新しく今までやったことのない品目に手を付ける。やったことのない品目なのに、大きな面積を転換してしまう。普及員でもデータを持っておらず、経験もないため、手探りのままの栽培となってしまい、失敗に終わってしてしまう。急激な変化には注意してほしいと思います。
②身の丈以上の投資
上記の規模拡大に関連しますが、今より利益を改善するには、大規模な投資が必要と思い込んでしまい実行してしまうケースがあります。 規模拡大で効率が悪化して収量を落とすだけでなく、投資には、借入金により行うことが多いため、返済の負担も増加します。
また、投資には補助金を活用される場合が多いですが、補助金をもらうためには、要件である規模拡大や正社員雇用、法人化、新たな販路開拓などがセットになりがちです。こうした要件をうまくクリアできる場合もありますが、経費増加が重荷になるケースが多く、大規模な投資の後にこうした要件に挑戦したものの、結果が出ずに経営が悪化するケースは非常に多いです。
③無理な雇用や問題のある雇用
無理な雇用とは、農家さんは何かご縁があり、正社員を希望する方が現れると、「これを逃すとせっかく応募してくれた人を逃してしまう」と思うのか、栽培規模を考えずに正社員で周年雇用を決断してしまう。一定以上の規模があればいいのですが、農業には農閑期があり、周年雇用はどうしても経費負けしてしまいます。法人化していれば社会保険料もかかります。しかも、2026年からは企業規模に関係なく、週20時間以上働き、月額賃金が8.8万円以上などの条件を満たすパートさん全員が社会保険の適用対象となる見込みなので、ますます固定費が増えいきます。
また、問題のある人材を雇用するのも経営を悪化させる要因になります。役員とパートさんの関係性には気を付けるべきです。パートさんの人数が増えてくると、一部のベテランパートさんの地位が上がっていくため、新人や作業の遅いパートさんに指導という圧力をかけてしまい、人材が定着しなくなっていきます。人数が増えると派閥化が進んでいきます。人の問題は放置していくと解決することが難しくなっていきます。
④原価とかけ離れた契約販売
「6次化や直接販売、契約販売をすることで農家の所得が上がる。」
こうした事例を常に農業新聞やネットで目にする方も多いかと思います。しかし、原価を計算せずに取引先の提案どおりに契約してしまい、経営が悪化している方を目にすることがあります。業務用の契約も注意が必要です。一見、規格選別が緩くなるため、価格が安くても手間が減るのでメリットがありそうだ、と感じて契約してしまうケースもよく目にします。 筆者が材料費、労務費、配送費、減価償却費などの固定費を計算すると、400円/kgの原価がかかっているのに対して、契約は280円/kgでしているケースがありました。これを数字で説明しても、現実を見ようとせずにそのまま契約を進めてしまい、1年以上続けてようやく見直しを始めてくれた方もいます。おそらく、取引先と価格の交渉をすることが相手との関係を悪くするため、言い出せないまま時間が過ぎてしまったのでしょう。その間にも経営は悪化の方向へ進んでしまいます。
⑤事業主が一人で背負い決断
最後は、栽培規模や雇用、販売価格、投資など大事な意思決定を、事業主である父や旦那さんが一人で決断してしまうことです。家族に相談すると反対されるため、決定してから事後報告というケースをよく目にしてきました。
最終的には何とかなることもありますが、経営が悪化しても、家族はそのことを父や旦那さんに責めると喧嘩になるので、誰も言い出さない(言い出せない)。父や旦那さんは資金繰りが悪化しても、ぎりぎりの状態になるまで外部にも相談しない。非常によくないパターンです。
今までは、このような経営が悪化する特徴があったとしても、何とか乗り越えられた時代だったかもしれません。ですが、毎年の異常気象や家族の高齢で、今までどおりの作業ができなくなった。人員補充のための人件費は上昇している。インフレで材料費や燃料費も値上がりしています。よって、今までとは違い、農家経営の難易度は上がっています。だからこそ、まずは「やってはいけないこと」をしないように注意してほしいです。
そして、
「応募してくれた社員を逃すと次はない。今しかない!」
「この補助金を逃すと次はない。今しかない!」
「規模拡大をしないといけない。今しかない!」
「投資をすれば効率がよくなる。今しかない!」
こうした判断を誤ってしまう「今しかない!」という状況に、安易に流されないようにしてほしいと思います。
以上