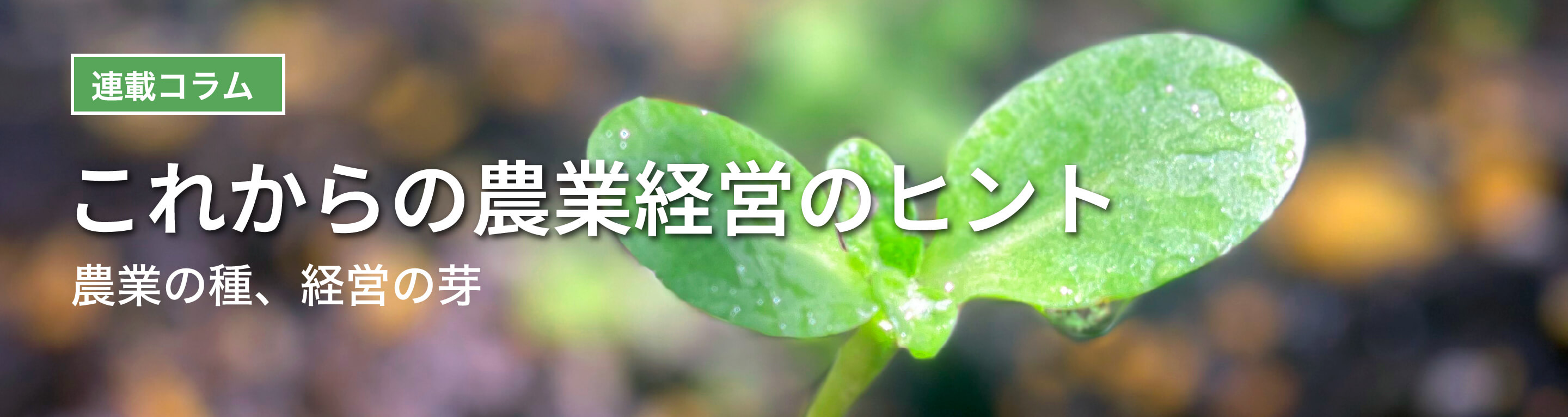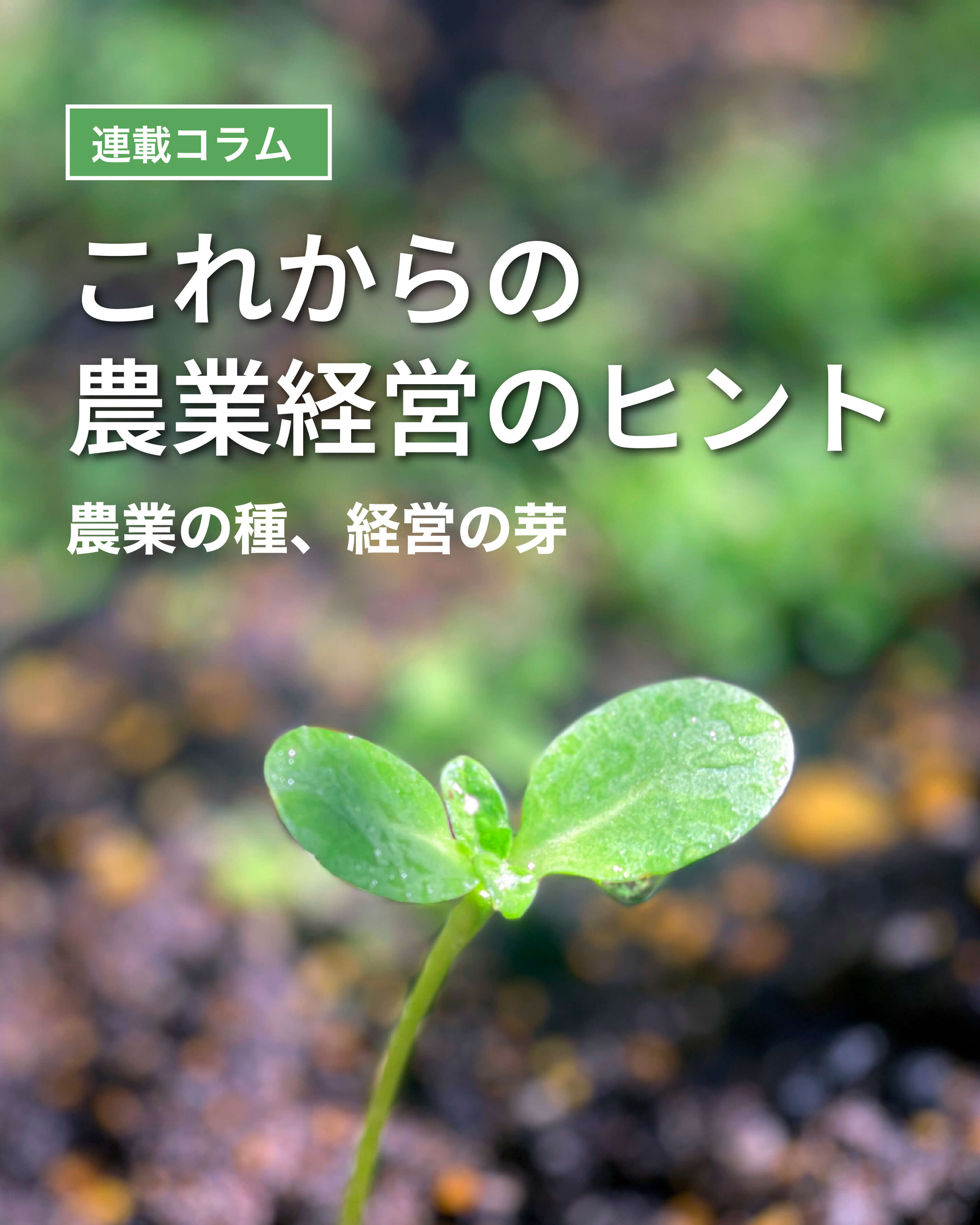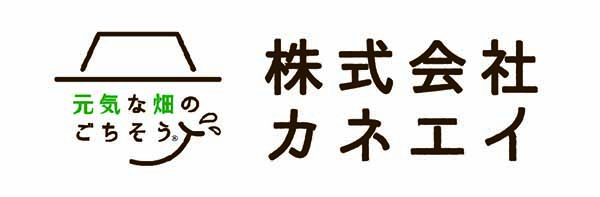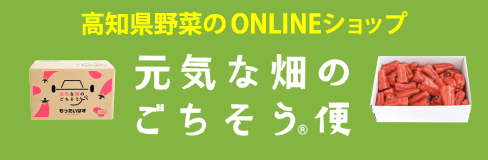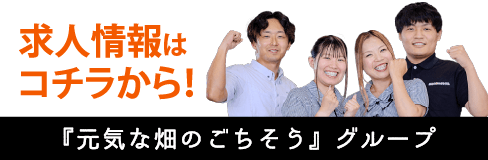損益計算書をエクセルで入力する意味
確定申告が終わって売上高の分析の次にすぐにやってほしいことがあります。それは、できあがった損益計算書をエクセルに打ち込んで欲しいのです。
できあがった決算書を見てもどう活用していいか?分からない方も多いかと思います。まずは作成した家族以外の人が見てもピンとこないこと。作成した本人であっても、会計ソフトや手書きなどで作成することに精一杯なので、できあがった数字を見てもどう説明していいのか分からない方も多いように思います。
筆者は、農家さんと面談をする際に、事前にいただいた複数年の決算書をエクセルに打ち込む作業をします。売上高から入力するわけですが、作付の規模や農作業をどのくらい頑張っているのか、金額の大きさを見れば大体わかります。
経費もそうです。
「肥料代がずいぶんかかっているけど値上がりしたのか?」
「修繕費の金額から本年はハウスや機械の部品を交換したのか?」
「施設は老朽化しているのだろうか?」
「労務費の額から正社員やパートがどのくらいいるのか?」
これらも、金額の大きさを見れば大体わかります。
エクセルに入力していると、数字からいろいろな現場の情景が不思議な事に頭の中に広がっていきます。これは、できた資料を眺めるよりも一つ一つ数字を入力し直すことで頭への入り方、その方の経営の様子がより具体的に入ってくるのです。
数字は、一つ一つの経営判断の積み重ねです。そこから経営者の意思決定の癖から性格まで見えてきます。たまに「初対面なのになぜそこまで分かるのですか?こわいです」と言われることもあります(笑)。
第三者の私ですらそこまで感じるのですから、事業主や家族の方がエクセルに入力することで私以上に現場の出来事が詳細にご自分の頭に入ってくるはずです。一つ一つの数字を入力する時間を苦痛と思わずに、現場を思い出しながら数字と紐付ける大切な時間になるよう、丁寧に思い起こしながらエクセルに入力してみてほしいのです。
損益計算書の構成
エクセルで入力する際に損益計算書の構成を知っておくといいです。
次の表が、損益計算書の構成です。
| 売上高① | 農産物の販売によって得た収入 |
| 製造原価(売上原価)② | 材料費、労務費、製造経費の合計 |
| ➥材料費 | 種苗費、肥料費、農薬衛生費、諸材料費、出荷資材など |
| ➥労務費 | 賃金、雑給、厚生費、作業衣料費など |
| ➥製造経費 | 動力光熱費、修繕費、減価償却費、地代、賃借料、農具費、共済掛金、車両費、租税公課 |
| 売上総利益③(1番目の利益) | ③=①―② |
| 販売費および一般管理費④ | 販売するための経費と経営全体にかかる経費 販売手数料、運賃、支払手数料、事務消耗品費、租税公課、旅費交通費、接待費、通信費、専従者給与など |
| 営業利益⑤(2番目の利益) | ⑤=③―④ |
| 営業外収支⑥ | 受取利息、受取配当金、補助金、雑収入など |
| 営業外費用⑦ | 支払利息など |
| 経常利益⑧(3番目の利益) | ⑧=⑤+⑥―⑦ |
| 特別利益⑨ | 受取保険など |
| 特別損益⑩ | 固定資産圧縮損など |
| 税引前当期利益⑪(4番目の利益) =青色申告課税所得 |
⑪=⑧+⑨-⑩ |
「うわ~、難しそう…」と思った方もいるかもしれませんが、細かい経費の名前よりもまずは損益計算書の大まかな構成を知ってほしいのです。
農家の皆さんは、製造業でもあります。材料を畑に投入して、人の手で加工して、農地や機械などを使って農作物を一つの製品として作っているのです。ですので、この3つを合計して製造原価でいったん集計します。
そして、売上高から製造原価を引くことで、1番目の利益である売上総利益を求めます。これを別名「粗利益(あらりえき)」ともいいます。この売上総利益は現場の変化に一番敏感に反映する利益です。天候や相場、雇用の増減、肥料や燃料代の価格変動など、現場で起きたことが反映します。この売上総利益が毎年増えたか?減少したか?具体的な数字で知ることは大事になってきます。
その次に、販売費及び一般管理費ですが、これは製造原価以外の経費と思ってもらってもいいです。販売費及び一般管理費は、略して「販管費(はんかんひ)」と呼ばれることもあります。販管費は、販売費と一般管理費の2種類で構成されています。
販売費というのは、販売するための経費と捉えてください。代表的な経費は販売手数料で、これは皆さんよくご存じの青果市場やJA、農産物直売所などの手数料です。それ以外にも運賃やインターネット販売での諸費用や百貨店の催事などで使った旅費なども入ります。
一般管理費というのは、経営全体にかかる経費と考えてもらうといいです。代表的なのは専従者給与です。農作業をしている家族への賃金は、製造原価の中の労務費に入れたいところです。でも、家族は経営者の一員である役員を考えられるため、こちらの一般管理費に入ります。あとは事務所の経費、営業車両の経費、前年の消費税の租税公課なども入ります。
1番目の利益である売上総利益から販売費および一般管理を引いた2番目の利益を、営業利益といいます。この営業利益は「どれくらい稼げたか?」が分かる大事な利益です。園芸や花き、畜産の場合は黒字にしないといけない利益ですが、稲作など土地利用型の農業は営業利益がマイナスになる方も多いです。その理由は、転作作物の売上高は単価が低いから。ですので、その下にある営業外収益の補助金で賄っています。
2番目の利益に営業外収益と営業外費用を差し引いた利益が3番目の利益である経常利益です。経常利益は、別名「けいつね」と呼ぶこともあります。農業は補助金も大事な収益ですから、これも加味して毎年の利益として考えます。その年の収益力を見るので、皆さんだけでなく、株主や銀行や行政の方など外部関係者も注目する大事な利益です。
経常利益の下にある特別利益と特別損益は、通常の年とは違う動きを別に分けることで、事業者に起こった出来事が外部からも分かるようにしています。災害などで収入保険が入ってきた場合や、出資金や固定資産を売却して利益が出た場合は、特別利益に入れていきます。特別損益は、補助金で設備や機械を買ったときに固定資産圧縮損を計上した場合や、災害で固定資産を除却した場合などに固定資産除却損として入れていきます。
こうして、経常利益とは別にすることで、その年に起こった出来事が分かるわけです。
最終的な利益が4番目の利益で、税引前当期利益といいますが、この4番目の利益と皆さんが申告する青色申告控除前の課税所得が一致するわけです。
1番目の利益 『売上総利益(粗利益)』
2番目の利益 『営業利益』
3番目の利益 『経常利益』
4番目の利益 『税引前当期利益』
この大きな4つの利益をまずは押さえましょう。もちろん、冒頭でお話したように、現場を感じるためにエクセルに入力するわけですから、売上と経費を差し引いた利益として入力してもいいですし、確定申告書の収支計算書で入力してもいいです。
できれば、今後もこの損益計算書の見方も解説していくので、そのためにもこの4つの利益をまずは覚える、そしてこの順番でエクセルに入力してみましょう。会計ソフトを使っている方は、会計ソフトの中で、集計などの項目の詳細で、「決算書」か「合計残高試算表」を選び印刷するとこの様式で出てくるはずです。
次回は、入力する手順や活用の仕方をお話します。
以上