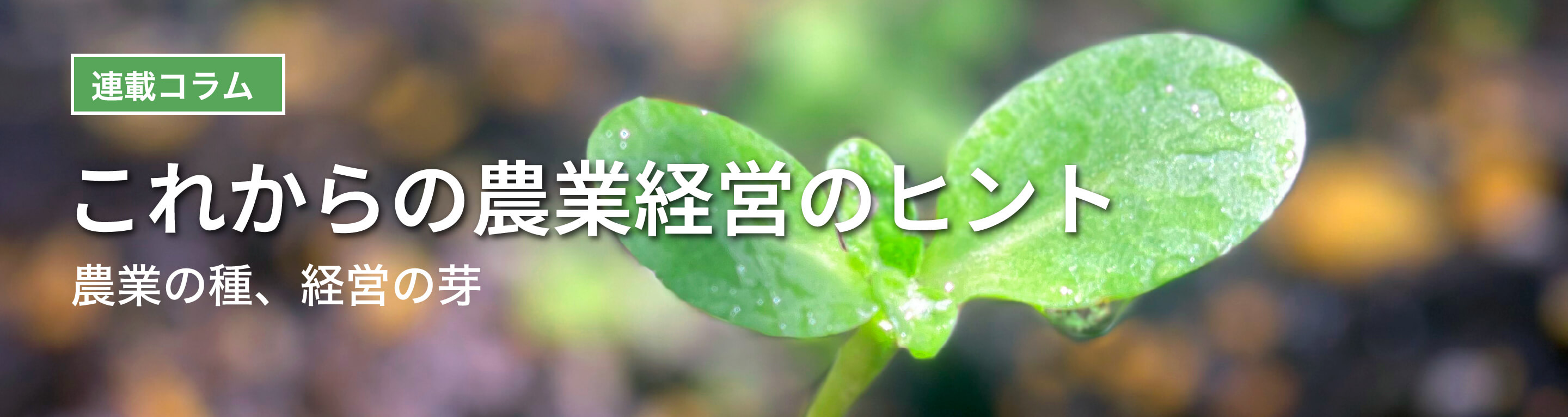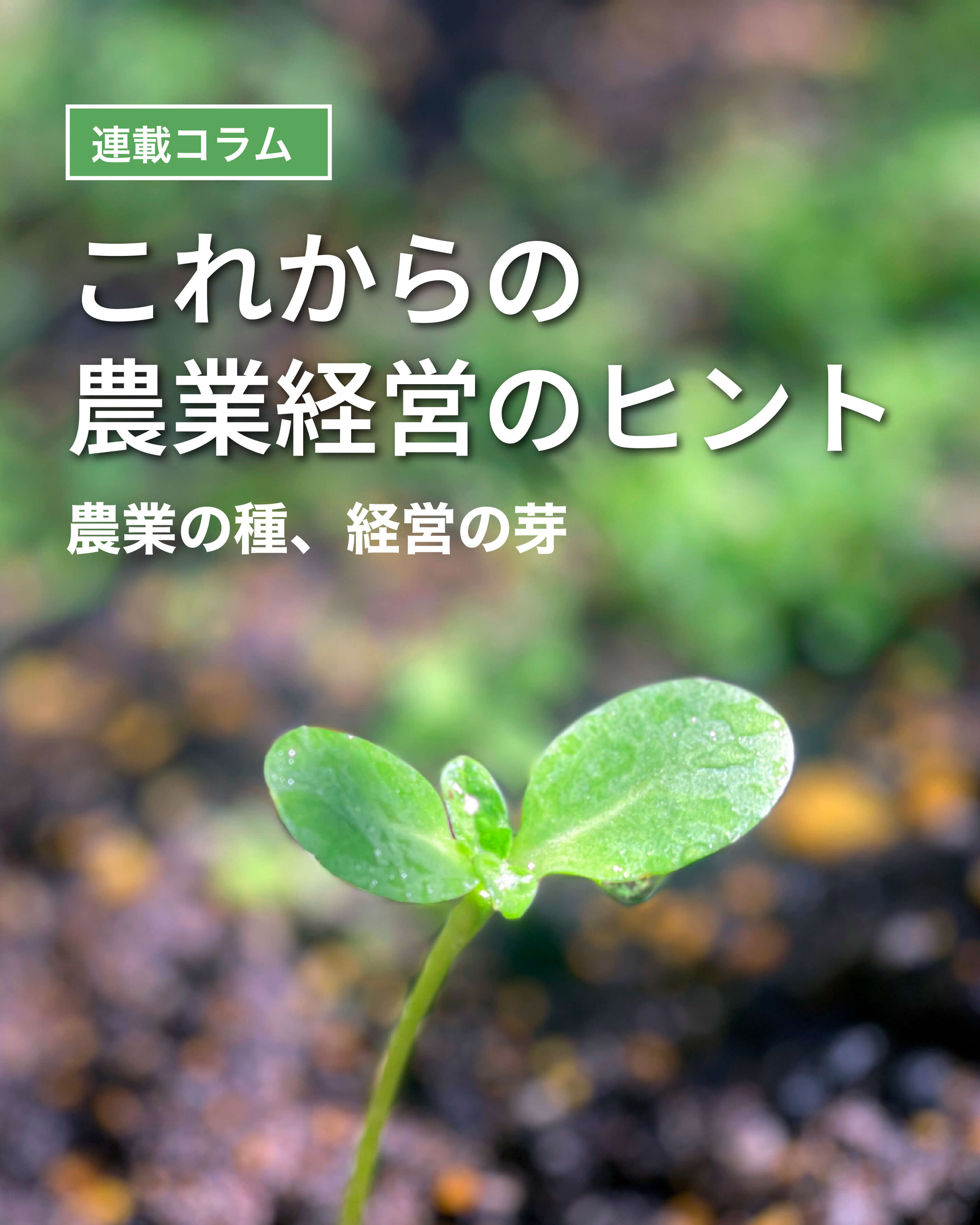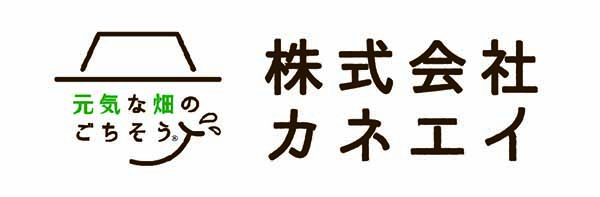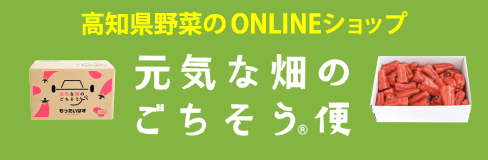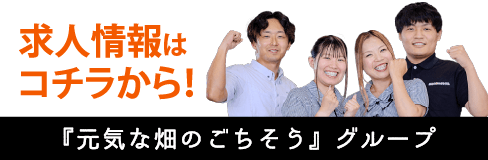家族で数字を共有する
これまでのコラムでは、決算書の分析やエクセルでの入力方法について解説してきました。今回は、これらの作業を終えた後、ご家族で集まって経営状況を共有し、話し合うための具体的な方法についてご紹介します。
1.売上について共有する
まずは、売上高について、前年と比較してどれくらい増減があったかを確認しましょう。可能であれば、過去5年間の売上高と比較して、今年がどのくらいの位置づけになるのかを把握できると、経営状況をより深く理解できます。
ここで、第3回でご紹介した「売上の分解」の表が大いに役立ちます。売上が変動した場合、その要因が面積の変化なのか、反収の増減なのか、あるいは販売単価の変動なのかを具体的に分析することで、売上増減の背景にある要因を明確にすることができます。
もし、「売上の分解」の表が作成できていなくても、過去の状況を振り返りながら、家族で話し合うことが大切です。
このように売上について話し合うことは、家族全員が売上高を把握することに繋がります。経営のトップであるお父さんは売上高を把握していても、奥さんや息子さん夫婦は必ずしもそうでないケースが見られます。
毎年、家族全員で集まって売上高の増減とその要因について話し合うことで、家族全員が経営状況を共有し、数字に対する意識を高めることができます。このことがとても大事だと思います。
2.最後の利益を確認してトレンドをみる
次に確認するのは、最終的な利益です。
第4回で損益計算書の構成について解説しましたが、利益には主に、売上総利益、営業利益、経常利益、そして当期利益(青色申告控除前課税所得)の4つがあります。
ここでは、特に当期利益に注目して、損益のトレンド(傾向)を把握しましょう。損益のトレンドは、一般的に以下の5つのパターンに分類できます。
- ●増収増益: 売上高と利益が共に増加している状態
- ●増収減益: 売上高は増加しているが、利益は減少している状態
- ●減収減益: 売上高と利益が共に減少している状態
- ●減収増益: 売上高は減少しているが、利益は増加している状態
- ●現状維持: 売上高、利益共に大きな変化がない状態
これらのパターンの中で、農業経営において特に多く見られるのが「増収減益」です。
その背景には、後継者のいる担い手への農地集約化に伴う雇用増加、新しい農地での反収低下、雇用増加による労働効率の低下、設備投資に伴う減価償却費の増加など、様々な要因が考えられます。
もちろん、栽培が順調に進み、単価も高ければ「増収増益」となることもあります。
この1年がどのような年であったかを、売上高と最終利益の増減から判断し、トレンドを把握することが重要となります。
3.売上総利益の増減をみる
売上高と損益のトレンドを把握したら、次に確認するのは、1番目の利益である売上総利益の増減です。
売上総利益は、農業の現場の状況が最も反映されやすい利益です。売上総利益の増減要因を分析するために、製造原価の内訳を見ていきましょう。
ここで、エクセルで作成した損益計算書が役立ちます。前年との比較や構成比を見ることで、どの勘定科目の金額が大きく変動しているかを発見できます。
例えば、肥料代が大幅に増加している場合、「なぜ肥料費が増加したのか?」という疑問が生じます。修繕費が増加している場合は「どのような設備を修繕したのか?」という疑問が浮かび上がるでしょう。
このような場合は、会計ソフトの元帳のメニューを開いて、肥料代や修繕費の内訳を確認することで、原因を特定することができます。これらの情報を家族全員で共有することで、前年の現場で何が起こっていたのかを具体的に理解することができます。
また、売上高は増加しているにもかかわらず、労務費がそれ以上に増加しているような場合には、構成比を比較することで、労働効率が悪化していないかを確認することが重要です。 特に、労務費や燃料費など、金額の大きい科目の構成比を前年と比較することで、経営上の課題が見えてくることがあります。
4.営業利益をみる
営業利益についても、売上総利益と同様に確認します。
営業利益は、農業の現場以外で発生する経費が反映されるため、売上総利益と比較すると、変動要因となる科目は少ないかもしれません。
しかし、荷造運賃や接待交際費、旅費交通費などに、不必要な支出がないかを確認することは重要です。
これらの経費項目をざっと確認するだけでも、無駄な支出を抑えるヒントが見つかることがあります。
5.経常利益をみる
経常利益は、雑収入の増減によって大きく変動する可能性があります。
特に、農業経営においては、補助金が雑収入として計上されることが多いため、経常利益を確認する際には、補助金の金額や内容を把握することが重要です。例えば、稲作農家で転作面積が大きい場合には、補助金の金額も大きくなる傾向があります。
肥料や燃料価格の高騰対策、災害復旧、雇用促進、設備投資など、様々な目的で補助金が交付されます。
したがって、経常利益を確認する際には、会計ソフトの元帳機能を使って、どのような補助金が交付されたのか、その明細を確認しましょう。
さらに、当該補助金が単年度限りのものなのか、次年度以降も交付されるものなのかを家族で共有しておくことで、将来の経営計画を立てる上で役立ちます。
6.次年度の目標を考えてみる
最後に、ここまでやってきた内容をもとに、次年度の目標を考えてみましょう。
- ✧売上目標はどのくらいにするか?
- ✧経費の抑制策はあるか?
- ✧労働力の確保や作業効率の改善策は?
- ✧新しい作物や販売方法の導入は可能か?
これらを具体的に話し合い、家族全員で共通認識を持つことが、よりよい農業経営につながります。
まとめ
このように、利益の段階ごとに気になる値を把握し、元帳などを参照しながら家族で話し合うことで、数字とその実態を結びつけることが大切です。
私は常々、農家の皆様に「数字を無理に分析する必要はありません。家族で話し合う機会を持つことが大切なのです」とお伝えしています。
まずは、売上高の増減、売上高と利益のトレンド、各勘定科目の気になる値、補助金の交付明細などを確認することから始めましょう。
これらの情報を確認していくことで、増収増益や増収減益の要因が明確に分からなくても、いくつかの気づきが得られるはずです。
私自身も、農家の皆様との面談で、数字を一緒に振り返る時間を大切にしていますが、数字と現場が繋がることで、非常に喜んでいただいています。
ぜひ、皆様も決算が終わった際には、ご家族で集まって経営状況を振り返る時間を作ってみてください。
以上