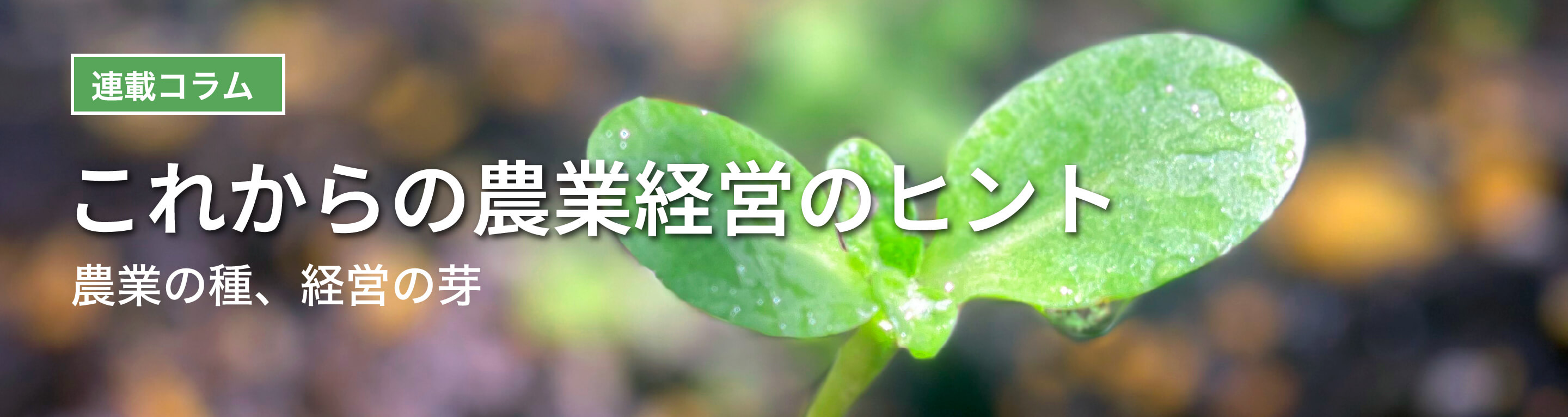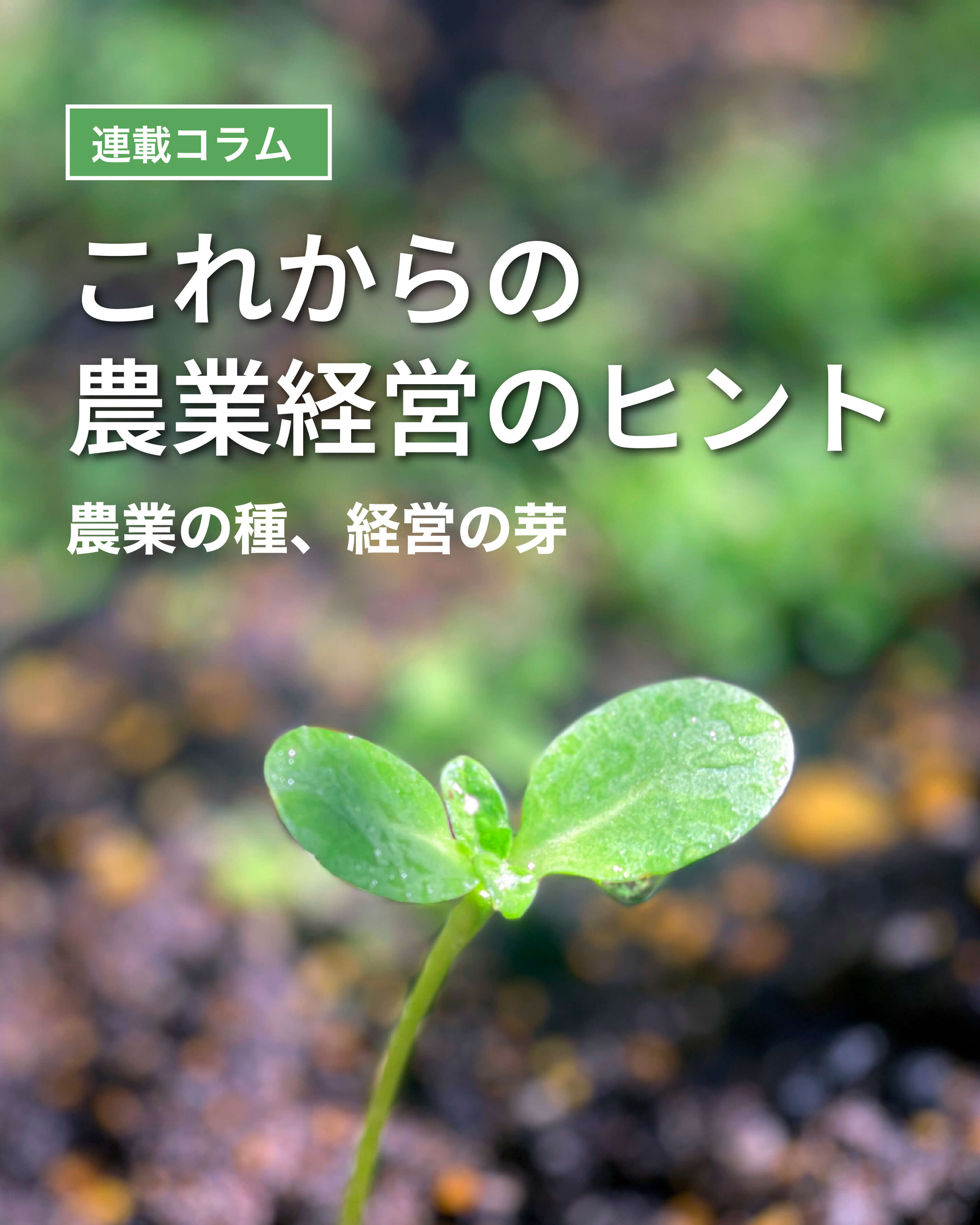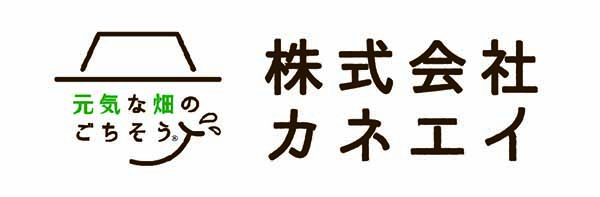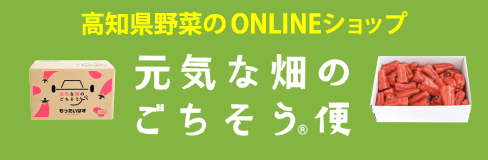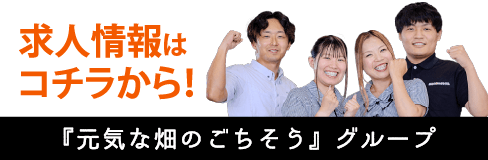売上分析のススメ
1月から2月のこの時期は、確定申告に向けて会計入力を頑張っている方も多いかと思います。第1回の連載でも触れましたが、私が指導している農家の皆様には、会計入力をなるべく早く終わらせて、まとめた数字を基に、経営分析や本年の作業計画などをこの時期に家族間で話し合うことを薦めています。今回は、「決算が終わったら、やってほしいこと」の具体的に説明します。
売上分解で経営改善のヒントをつかむ
まず、やってほしいのは、前年の売上の分解です。私が損益計算書を見て、大きな不満を感じることがあります。それは、売上が金額のみしか表示されていないことです。経費の項目はたくさんあるのに、売上項目はたったの1行のみです。この売上高は、分析することで経営をよくするためのヒントがたくさん詰まっています。
売上高は、次のように分解できます。
売上高(金額)=数量(kg)×単価(円/kg)
売上高は、皆さんが確定申告をするために集計しますので、皆さんが一番よく分かっています。なので、シーズンでどのくらいの数量を出荷したのか、総出荷数量を記録してください。総出荷数量は、出荷したJAや市場に問い合わせをすれば、出荷総数量と売上高が記載された集計表をくれるはずです。それ以外の直販場で販売した数量は、これは少し大変かもしれませんが、ご自分の出荷伝票などを集計する必要があります。複数箇所に出荷している方は、それぞれから入手した集計した数量を合わせれば、自社の総出荷数量が出せるはずです。
数量が分かれば、平均販売価格が出せます。
単価(円/kg)=売上高(金額)÷数量(kg)
また、皆さんは自分の作付面積を把握していますから、以下の式で反収(kg/10a)が求められます。
反収(kg/10a)=数量(kg)÷面積(10a)
こうして、出荷数量を集計することができれば、以下のような表が完成します。
| 前年度 | 本年度 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 面積(10a) | |||
| 反収(kg/10a) | |||
| 数量(kg) | |||
| 単価(円/kg) | |||
| 金額(円) |
ここで注意してほしいのは、集計する期間です。確定申告の期間は1月~12月です。この期間で集計しても構いませんが、高知県のように作型のシーズンと申告の期間が違う場合は、どちらかに統一する必要があります。売上高の分解については、作型の期間でこの表を作成する方がいいかもしれません。ナスなら9月~8月みたいな感じです。
売上分解でわかること
数量の集計をするだけで、シーズンの平均単価がどうであったか、反収がどうであったか、数量がどうであったか、その結果、売上高(金額)がどうであったか、前年と比較することで、このように数字で振り返りをすることができます。
近年の動向をみると、異常気象や夏場の高温によって、反収(kg/10a)や数量(kg)が減少し、単価(円/kg)が上がる傾向にあると考えられます。しかし、農家さんによっては同じ気象条件でも反収(kg/10a)に差が見られます。細かい管理の仕方や対策を事前に行うことで、悪い影響を最小限にしている方もいます。
また、規模拡大に向かうと、反収(kg/10a)は減少する傾向があります。これは、管理する範囲が増えてベテランの家族やパートさんだけでは賄えなくなり、新人のスタッフを入れた結果、技術の差や栽培管理の共有で問題が生じるためです。
単価(円/kg)においても、近年は相場が高くなる傾向にありますが、農家さんによっては良い品質で出荷できる方は出荷等級も良くなるため、平均単価に差が出てきます。
大事なのは、この傾向を何となく把握するのではなく、売上を分解してきちんと数字で把握することです。そして反収(kg/10a)や単価(円/kg)についてどのくらい増加または減少したか、その要因は何だったのか、このことを家族間やスタッフとミーティングして、ゆっくりと話合う機会を作ることが大事です。
月ごとの売上分解でさらに深い分析を
さらに、月ごとに分解できると、更に深い議論ができるはずです。
| 本年度 | 前年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 (kg) |
単価 (円/kg) |
金額 (円) |
数量 (kg) |
単価 (円/kg) |
金額 (円) |
|
| 9月 | ||||||
| 10月 | ||||||
| 11月 | ||||||
| ・・・ | ||||||
| 8月 | ||||||
| 合計 | ||||||
「病気が発生してしまった。」
「繁忙期に手が足りなくなって、数量を落としてしまった。」
「次年度は、事前に人手を集めて管理を徹底しよう。」
「予防の農薬対策をしっかりとやろう。」
家族で月ごとの数量を把握し、当月の目標を明確にすることで、行動に変化が生まれて反収(kg/10a)が上がることにつながっていきます。
この表は毎月の記録が大事になってきます。すぐには難しいかもしれませんが、やりたい方は本年からでも毎月集めていくといいかと思います。
売上の分解をして、家族間でスタッフとのミーティングにぜひ役立ててほしいです。これだけで数字は変わっていきます。
次回は、「損益計算書をエクセルシートに入力すること」の必要性について解説したいと思います。
以上